杉並木を永続させることについて着実な整備実施を、針広混交林については自然遷移に委ねることを基本にしています。
具体的には、以下のような方針をもって整備を行っていきます。

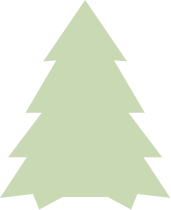
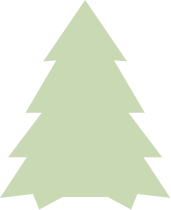
【戸隠杉並木の継承計画】
杉並木を永続させることについて着実な整備実施を、針広混交林については自然遷移に委ねることを基本にしています。
具体的には、以下のような方針をもって整備を行っていきます。
●補植事業
倒木箇所への新たな杉の植樹
●遺伝子保護
現地の杉から挿し木で育成した苗木を使用
●環境整備
広葉樹の枝払いや伐採による日照確保
●土壌改良
杉並木の健全な成長のための土壌環境改善
400年の歴史を持つ戸隠の杉並木を未来に残すため、現在の老木と全く同じ遺伝子を持つ「クローン」の苗木を育てています。
方法:
現在の杉並木から枝を採取し、戸隠以外の安全な場所で挿し木によって苗木を育成。古いスギが枯れた時に、この育てた苗木を植えて杉並木を継続します。
今後の課題:
令和4年の植栽実験結果をもとに、植える間隔、苗木の大きさ、植え替えのタイミングなどの詳細を決定予定です。
これにより、400年間守られてきた杉並木の「血筋」を絶やすことなく、永続的に美しい並木を保全していきます。


補植のタイミング:
スギ同士の間隔が20m以上空いて、残った木の枝が伸びても隙間が埋まらない場合のみ実施。
1本だけ枯れた場合は、新しい苗木が育たないので植えません。
植える場所の配慮:
枯れた木の根は抜かず、少しずらした位置に植栽。杉並木の周りは貴重な史跡のため、遺跡を壊さないよう史跡専門家の立会いで慎重に作業します。
場所別の注意点:
院坊跡側は現在の列を維持、講堂川側は参道から少し離れた位置に植栽。
実施体制:
樹木と史跡の両方の専門家が参加する協議会で十分議論し、法的手続きを経て実施します。


対象となる木:
参道側に傾いていて、倒れると参道を塞いでしまう可能性がある杉の木が対象です。
危険と判断する基準:
普通の雪や風でも倒れそうな状態で、地元の人と外部の専門家が話し合って「やむを得ない」と判断した場合のみ、伐採を検討します。
手続き:
危険と判断した理由を詳しく記録し、正式な手続きを経て伐採します。台風などで実際に倒れた場合は、参拝者の安全のため緊急に対応できます。
その後の対応:
伐採した後は必ず新しいスギを植えて、杉並木が長期間失われないよう配慮します。
伐採する木の条件:
スギの木の上(樹冠)に覆いかぶさって、スギの成長を邪魔している広葉樹だけが対象です。
伐採しない木:
スギの木の上に重なっていても、スギの枝の下で葉を広げている木は、スギの成長に悪影響がないので切りません。
対象範囲:
スギの幹から半径5メートル以内にある木で、上記の条件に当てはまるもののみ、枝払いや伐採を検討します。
つまり、スギの木が太陽の光を十分に受けられるよう、本当に邪魔になっている木だけを最小限取り除くという方針です。
スギの下で育っている木や、離れた場所にある木は、自然のままにしておきます。
基本的な考え方:
スギや他の木が、貴重な史跡(昔の建物跡など)を明らかに傷つけている場合のみ、最小限の手入れを行います。
実施方法:
史跡や植物の専門家たちがしっかり話し合って決めます。
その木がなぜそこに生えているのか(例:昔の院坊の人が食べ物や薬のために植えた木など)を調べます。
自然の状態や木の種類も考慮して、適切な手入れ方法を検討します。
大切なポイント:
史跡を守ることと自然を守ることの両方を大事にしながら、本当に必要な場合だけ、専門家の判断で慎重に作業を行います。
つまり、昔の人々の生活の痕跡である史跡と、長い間育ってきた自然の両方を大切にバランスよく保護するということです。
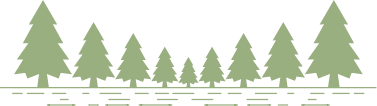
“ご支援のお願い”


受け継がれてきた聖域を、次世代へ。
神聖な自然と文化を後世に伝える保全事業。
参拝者・地域・企業が一体となった保全活動を目指していきます。