戸隠神社信仰遺跡は、昭和54年(1979年)3月22日に長野県史跡に指定された遺跡で、戸隠神社奥社叢では、随神門から奥社に至る参道の両側約110mの地域が対象となっています。この史跡は「修験の道場として山岳宗教の形態等を知るうえで貴重な遺跡」として評価されています。

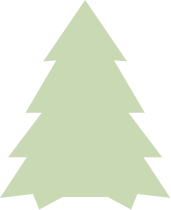
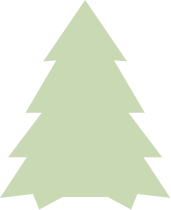
戸隠神社信仰遺跡は、昭和54年(1979年)3月22日に長野県史跡に指定された遺跡で、戸隠神社奥社叢では、随神門から奥社に至る参道の両側約110mの地域が対象となっています。この史跡は「修験の道場として山岳宗教の形態等を知るうえで貴重な遺跡」として評価されています。
戸隠の宗教的起源と発展
●平安時代初期(9世紀)
戸隠の宗教的歴史は、平安時代に成立した『阿娑縛抄』に収められた「戸隠寺縁起」によると、仁明天皇の嘉祥年間(820年頃)に学問行者が修験を始めたことから始まります。
●平安時代中期の発展
●平安時代中期の発展
●戦国時代の試練と筏が峰移転
武田・上杉の争乱
戦国時代になると、戸隠山は武田氏と上杉氏の争乱に巻き込まれ、絶えず存亡の危難に脅かされました。
帰山と復興
●江戸時代の体制確立
徳川幕府による統制
院坊制度の発展
参道と院坊の整備
●明治維新と廃仏毀釈
戸隠山顕光寺から戸隠神社へ
現在の史跡は、この明治維新の際に撤去された院坊の跡であり、江戸時代末期に描かれた『信州戸隠山惣略絵図』の姿から建物等が撤去され、スギ並木の参道だけが残った状態です。
史跡の学術的意義
戸隠神社信仰遺跡は、以下の点で学術的に重要です。
●発掘調査で明らかになった遺構
講堂跡の発見
院坊跡群の配置
参道の南には11院があり、奥社より神原(観法院)-今井(金輪院)-水野(常楽院)-太田(妙光院)-京極(妙観院)-成瀬(成就院)-奥田(真乗院)-安藤(安住院)-常田(常泉院)-渡辺(仏性院)-松井(妙智院)となっていた。現在確認できる院坊跡の特徴は以下の通りです。
講堂跡の重要性
講堂跡は、九間×五間の大規模な建造物のあったことが礎石の配列状況で確認され、年代は出土品により鎌倉時代前後と推定されている。
この講堂は山岳信仰の拠点であった可能性が強く、『戸隠山顕光寺流記』に、1098年(承徳2年)に奥院に講堂が設けられたとある記録と符合します。
戸隠の史跡は、日本の山岳信仰と修験道の歴史を物語る貴重な文化遺産として、天然記念物である社叢とともに保存されている極めて稀有な事例といえます。
日本の山岳信仰の歴史を物語る史跡と、信仰によって守られてきた自然が一体となった、国内でも類例の少ない極めて貴重な文化遺産として、総合的な保全が求められています。
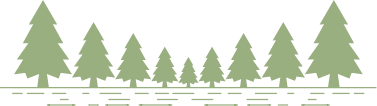
“ご支援のお願い”


受け継がれてきた聖域を、次世代へ。
神聖な自然と文化を後世に伝える保全事業。
参拝者・地域・企業が一体となった保全活動を目指していきます。