一般財団法人「戸隠奥社の杜財団」は、戸隠神社奥社及び周辺地域、戸隠神社奥社社叢及び戸隠神社信仰遺跡の自然環境と文化財の調査・研究、それらの保存と活用に係る整備及び普及啓発等の事業を行い、地球環境の保全、文化の創造に寄与することを目的に、この杜の管理団体として、戸隠神社と一体で、杜の保存と活用に取り組んでいます。

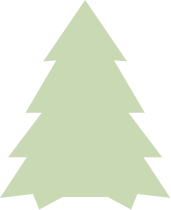
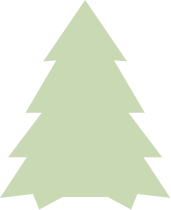
About
一般財団法人「戸隠奥社の杜財団」は、戸隠神社奥社及び周辺地域、戸隠神社奥社社叢及び戸隠神社信仰遺跡の自然環境と文化財の調査・研究、それらの保存と活用に係る整備及び普及啓発等の事業を行い、地球環境の保全、文化の創造に寄与することを目的に、この杜の管理団体として、戸隠神社と一体で、杜の保存と活用に取り組んでいます。
戸隠奥社の杜は、新潟・長野両県にまたがる妙高山、黒姫山、飯綱山など個性ある山々からなる妙高戸隠連山国立公園内に位置し、戸隠山直下に広がる約60ヘクタールの針葉樹と広葉樹の混交林で、戸隠神社奥社社叢として昭和48(1973)年、県の天然記念物に指定されました
戸隠山からは、鳥居川・楠川が、裾花川・犀川を経由して信濃川に注いでおり、米どころ新潟の平野を潤してきました。この山は、その峨峨とした稜線と急峻な断崖が打ち続く姿から、風雨を司る龍神の住むところとして、古くから水源の神、水の神としての信仰を集め、嘉祥(849)年、学門行者がこの地主神九頭龍神の加護により道場を開くに至りました。この道場が後に天台派(本山派)戸隠山顕光寺本院(奥院、以下奥院、現 奥社)の起源となったとされます。
奥院には天手力雄命も祀られ、その後、康平年間(1058頃)天表春命を宝光院(現 宝光社)に、寛治年間(1087頃)天八意思兼命を中院(現中社)に祀り、修験道の道場として栄えるようになったのです。
また、中世には天台派のほかに真言派(当山派)の修験も戸隠山西岳に道場を構えるようになり、山麓の繁栄ぶりは比叡・高野と並んで戸隠三千坊、三山三千坊と喧伝されました。
上杉・武田両軍の信越国境の争いによる混乱を経て、奥院は天台寺院戸隠山顕光寺の中心として、堂宇、参道が整備されていきます。参道には現在の杉並木の起源となる杉が植樹され、その延長線は、参道中間の仁王門(現 随神門)・参道入り口を経て辰の方角(東南東)に延びています。 それにより、立春と立冬には、杉並木から随神門の真上に昇る朝陽が望めます。
奥社地域を中心に、古くからの山岳信仰を伝える貴重な遺跡として中社・宝光社及び小川村の筏が峯三院跡(奥院跡・中院跡・宝光院跡)が、昭和54(1979)年に長野県史跡(戸隠神社信仰遺跡)に指定されました。
本天然記念物と本史跡の指定範囲は、随神門より奥院側の地域で重なっています。
| 昭和48年 | 戸隠神社奥社社叢が長野県により天然記念物に指定される。 |
|---|---|
| 昭和54年 | 奥社参道の中ほどに位置する随神門より奥社側が、長野県文化財保護条例により、 県史跡「戸隠神社信仰遺跡」に指定される。 所有者である戸隠神社において、「保存と活用の両立のあり方」の検討始まる。 |
| 平成21年 | テレビコマーシャルで奥社参道杉並木が取り上げられる。 |
| 平成22年 | 地域住民、専門家、戸隠神社からなる、奥社の杉並木を主な対象として保護活動を担う組織「戸隠奥社の杜と杉並木を守る会」(以下 守る会)発足。 守る会が奥社参道杉並木周辺の毎木調査を5年に一度、定期的に実施するほか、周囲長300cm以上を対象とした巨木調査等を精力的に学術的調査を重ね、戸隠神社奥社社叢の現状を詳細に記録、データで表現可能とする。 |
| 平成29年 | 超大型台風21号の影響で、杉並木のスギ3本を含む巨樹6本が倒れる。 これを契機に「保存と活用の両立のあり方」を関係者が議論し、信仰対象としての神社が永続して参拝客を安全に迎えることと、将来にわたり本天然記念物及び史跡が保存されることの両立を図る機運高まる。 |
| 令和元年 | 県知事への請願を経て、長野県及び長野市の補助を受け、本天然記念物の本質的価値を再定義し、保存と活用の方針を定める「戸隠神社奥社社叢保存活用計画」の策定が開始される。 |
| 令和5年 | 「戸隠神社奥社社叢保存活用計画」策定 同計画により、保存と活用に取り組むための体制については、戸隠神社と守る会が一層の連携を図り、同会の発展的な体制整備により持続可能な運営体制構築を目指すこととなる。 同じく、地元の観光協会をはじめ関係団体、本計画策定委員会に携わった専門家等からなる「長野県指定天然記念物戸隠神社奥社社叢保存活用協議会」(仮称)を設置し、本天然記念物の保存活用を行うこととなる。 |
| 令和5年 | 「戸隠神社奥社の杜協議会」設置 |
| 令和6年 | 「戸隠神社奥社社叢保存活用計画」に基づき奥社社叢の保存管理及び活用事業を推進するとともに、必要な計画更新のための調査・研究及び検討を行うことを目的とする。 令和6年 一般財団法人「戸隠奥社の杜財団」設立 戸隠神社奥社社叢及び戸隠神社信仰遺跡の管理責任者(管理団体)として、戸隠神社と一体で保存活用に取り組む。 理事会において、公益財団認定を目指すことを決議する。 |
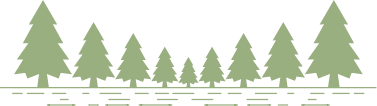
“ご支援のお願い”


受け継がれてきた聖域を、次世代へ。
神聖な自然と文化を後世に伝える保全事業。
参拝者・地域・企業が一体となった保全活動を目指していきます。